第七話 黄金の雷(13)
アンドレスは指先で涙を拭(ぬぐ)うと、そのまま、ふらつく足取りで天幕を出た。
天幕の入り口で警護にあたる兵たちが、彼に丁寧な挨拶を送る。
アンドレスは意識が半ばここにあらずではあったが、それでも、丁寧に挨拶を返した。
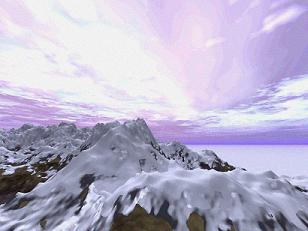
彼が見つめる先には、昨日、トゥパク・アマルの声を感じたあの大木が、白みはじめた早朝の天空を背景に、荘厳な気配を湛えながら風に揺れている。
(トゥパク・アマル様……昨日の声も、今、見たものも、幻や夢ではない。
本物のトゥパク・アマル様だった!!)
まさにその時、大木の向こうから、輝く太陽が、6000メートル級の霊峰の輪郭をくっきりと染め上げながら昇りくる。
生まれたばかりの眩い太陽が放つその光は、真っ直ぐに、アンドレスのもとに差し込み、真正面から彼を照らし出した。
遠目から見ると、まるで炎に包まれていくようなアンドレスの姿に、既に朝の活動を開始していた兵たちは眩しそうに息を呑む。
そんな自軍の兵たちに、アンドレスはゆっくりと視線を向けた。
そして、意を決した表情になる。
彼は拳を握り締めた。
「このまま、ソラータの包囲を続行する!!」
決然とした彼の言葉に、兵たちは深く恭順の礼を払った。
今、アンドレスは、どこかトゥパク・アマルを彷彿とさせる研ぎ澄まされた美しい目で、はるばると兵たちを見渡し、深く頷き返す。
だが、同時に、彼の心の奥底では、ドクドクと音を立てながら真紅の血が流れ出していた。
彼の胸の中で、氷のような冷たい、もう一人の己の声がする。
(アンドレス…おまえは、今、トゥパク・アマル様のお命を見捨てたのだ…――!!)
それから、アンドレスは急ぎ副官らを集め、数十名の精鋭の兵たちから成る部隊を幾つも編制し、当地に向かって避難を続けているはずのトゥパク・アマルの次男、皇子マリアノの捜索と救出に向かわせた。
使者の話から、マリアノが重臣ベルムデスと共に平民を装って当地に向かっていることも聞き及んでいたため、アンドレス軍の兵たちも平民になりすまし、決して目立たぬよう細心の注意を払いながら、幾つかのルートに別れて手分けをしながら捜索を続けた。
かくして、その数日後、ソラータの包囲網を固めながら祈るような気持ちでマリアノたちを待つアンドレスの元に、早馬の使者が飛ぶように馳せ参じた。
「アンドレス様!!
朗報でございます!!
マリアノ様が…!!」
使者の言葉に、アンドレスは軍議の席から、飛び上がるように立ち上がる。
その場にいた他の兵たちも、ハッとした表情で一斉に使者の方を見た。
アンドレスは使者の傍に駆け寄った。
「マリアノ様が…マリアノ様が、見つかったのか?!」
使者は迸(ほどばし)るよう笑顔で、「はい!!アンドレス様!!」と、息を切らしながら応える。
アンドレスは興奮と恍惚の表情で、思わず使者の両腕を握り締めた。
「マリアノ様は、ご無事であったか……!!」
あまりの深い安堵と歓喜のために、その声は上擦っている。
「はい!!
アンドレス様!!
まもなく、当地にご到着されるかと!!」
「そうか!!」
アンドレスは幾度も頷きながら使者の労をねぎらうと、そのまま、居ても立ってもいられぬという風情で、落ち着きなく天幕を飛び出した。
不意に、アンドレスの視線は、どっしりと大地に根を張り、風に悠然とその身をあずけているあの大木の方に動いた。
(トゥパク・アマル様!!
お喜びください!!
皇子様は…マリアノ様は、ご無事です!!)
彼の心の声に呼応するかのように、大木が、風の中で、太い幹を大きく揺らした。
今、その常緑樹の抱く一枚一枚の葉にキラキラと陽光が反射し、紺碧の天空を背景に黄金色の覇光を放つそのさまは、神々しいほどに荘厳で美しく、アンドレスは眩さに目を細めた。
(トゥパク・アマル様…!
トゥパク・アマル様も、喜んでおられるのだ……!!)
アンドレスの胸に、熱いものが込み上げる。

彼は、兎も角も軍議の席に戻ったが、まもなく、興奮を滲ませて天幕に飛び込んできた別の兵によって、再び軍議は中断された。
兵は息を切らしながら、輝くような瞳でアンドレスを見上げる。
「マリアノ様が、ご到着です!!」
「そうか!!」
アンドレスは、到着を知らせた兵の肩を叩いて礼を送ると、飛ぶような勢いで天幕から走り出た。
他の兵たちも、興奮に顔を紅潮させ、一斉にそれに続く。
天幕を抜けると、アンドレスは野営場の入り口に向かって走った。
(マリアノ様!!
本当によかった!!
ああ…インカの神々よ、感謝します…――!!)
彼が走っている間にも、野営場の入り口付近で、どよめきと共に歓声が上がるのが聞こえてくる。
「ご到着か?!」
アンドレスの歓喜の声に、入り口の方から走り込んできた兵が、「はい!!」と、力強い声で応えた。
殆どそれと同じ瞬間に、彼の精鋭の兵たちに守られるようにして馬に乗せられたマリアノの姿が、アンドレスの目の中に飛び込む。
逃亡のために扮した平民の服装は、もはやボロ布を纏っているがごとくの疲弊ぶりではあったが、馬上の少年は、まさしく皇子マリアノに相異なかった。
(マリアノ様!!)
互いに、まだ距離は離れていたものの、大きく瞳を輝かせて己を見つめるアンドレスの視線に、マリアノはすぐに気が付いた。
そして、彼も、また、馬上から真っ直ぐにアンドレスを見た。
二人の視線が完全に合う。

「アンドレス!!」
「マリアノ様!!」
トゥパク・アマルの皇子マリアノは、トゥパク・アマルの甥であるアンドレスとは、幼き頃から交流も深く、マリアノにとってアンドレスは年の離れた兄のような存在でもあった。
己の元に走ってくるアンドレスの来るのを待ちきれぬとばかりに、兵が手助けするのも待たず、マリアノは馬の背から臆することなく飛び降りた。
兵たちが、「危ない…!」と息を呑むその瞬間にも、マリアノは美しい姿勢で器用に着地すると、アンドレスの方に向かって一直線に走ってくる。
アンドレスも、一心にマリアノの元へ走った。
「マリアノ様!!!」
マリアノは真正面から、弾丸のようにアンドレスの胸の中に飛び込んだ。
アンドレスの逞しい腕が、しっかりとマリアノを受け留める。
「アンドレス!!
アンドレス!!
アンドレス――!!!」
アンドレスは激しく胸の奥が熱くなるのを感じながら、力強くマリアノを抱き締めた。
感極まって、すぐには声が出ない。
「…――マリアノ様!!
よくぞ…よくぞ、ご無事で…!」
しかと抱き合った後、アンドレスはマリアノの頬を両手で包み、感動に震える眼差しで少年の瞳を見つめた。
トゥパク・アマルに生き写しのマリアノの顔は、過酷な長旅のためにすっかりやつれ、皮膚も、髪も、どこもかしこも頭の天辺から爪先まで、余すところなく埃と土と汗にまみれている。
そのマリアノは、深い安堵と緊張からの解放からか、完全に脱力したようにアンドレスの胸にもたれかかっている。
実際、あまりの長距離を歩き続けてきたために、脚力も体力も限界に達していたのだ。
そして、それ以上に、精神的な苦痛が、マリアノの心と全身を蝕(むしば)んでいた。
それでも、彼は、ベルムデスと共に、諦めることなく、一寸の予断もならぬ危険な逃亡の道程を必死に進み続けてきたのだった。
父トゥパク・アマルをはじめ、母ミカエラや兄弟たちまでもが囚われた今、己が生き延びることがどれほど重要なことなのか、10歳とはいえ、利発な皇子マリアノは十分に認識しているはずである。
(マリアノ様…――!!)
アンドレスは、今ひとたび、マリアノの痩せ細った体を抱き締めた。
そんなアンドレスの腕の中で、マリアノは瞳に涙を浮かべながら、それでも、懸命に歯を食いしばって泣くまいとしている。
「アンドレス…父上だけでなく…母上も…兄上たちも、奴らに捕まって……!!」
アンドレスは胸を掻き毟(むし)られる心境で、マリアノの大きく揺れる瞳を見つめた。
アンドレス、父上たちを助けて…――!!と、マリアノの瞳が激しく訴えているようで、彼は反射的に目をそらした。
そして、その視線を避けるように、再び、強くマリアノを抱き締める。
「マリアノ様のこと、この俺が必ずお守りいたします。
たとえ、俺の命に代えても…!!」
それは、アンドレスの真実の思いであった。

(トゥパク・アマル様……!
あなた様のお命をお見捨てした俺に…僅かでも報いる機会をお与えくださったのか…――)
マリアノを懐深く抱き寄せ、泥土で強張った少年の髪に顔を埋(うず)めるアンドレスの横顔で、硬く閉じられた瞼が震えていた。
夢中でマリアノを掻き抱(いだ)くアンドレスの傍に、マリアノと同行していたベルムデスが、静かに近づいた。
ベルムデスもまた、マリアノ同様、泥と埃にまみれ、今となっては装わずとも、そのままで全く正真正銘の物乞いのごとくの風貌に成り代わり、よほど注意深く見なければ、誰か判別できぬほどであった。
しかも高齢のベルムデスにとって、マリアノを庇護しながらの此度の過酷な道程は、心底骨身に染みたに相違ない。
しかし、その深遠な知恵と慈愛に溢れた瞳の色はかつてと変わらず、一縷(いちる)も濁ることなく健在であった。
「ベルムデス殿…!!」
アンドレスの胸は、また熱く込み上げる。
ベルムデスは、アンドレスに深く礼を払った。
「アンドレス様、お久しゅうございます。
当地、ラ・プラタ副王領でのアンドレス様のご活躍、トゥパク・アマル様も深くお喜びであられましたぞ。
こうして、また相見(あいまみ)えることができようとは、なんと幸いなことでありましょうか!」
アンドレスも、再会の感動に極まった面差しで、マリアノを腕に抱いたまま、ベルムデスに深く礼を払った。
「ベルムデス殿、俺も、どんなにお会いしたかったか…!
それに…此度のマリアノ様のこと、何とお礼を申し上げてよいものか…!!」
ベルムデスは、そっと微笑み、頭を下げる。
再び顔を上げたベルムデスとアンドレスの眼差しが、しっかりと合った。
その瞬間、言葉にはならずとも、アンドレスの瞳は、深く物言いたげに、大きく揺れた。
必死で耐えようとしても、誰にとっても慈愛に満ちた祖父のごとくのベルムデスを前にして、思わず、アンドレスの瞳は潤みかける。
彼は、唇を強く噛み締めて、涙が落ちそうになるのを、ぐっとこらえた。

一方、老賢者ベルムデスには、一連のアンドレスの心境は、何も聞かずとも手に取るように理解できる。
ベルムデスはその温厚な、包み込むような眼差しで、ゆっくりと、ただ黙って頷いた。
(アンドレス様……。
さぞや、お辛いご決断であられたことでありましょう。
ですが、当地に残られたあなた様のご判断は、正しかったのです。
どうか、トゥパク・アマル様のことで、それ以上、ご自分を責められますな)
唇を噛み締めながら己を喰い入るように見つめるアンドレスに、ベルムデスは、もう一度、しっかりと頷き返した。


